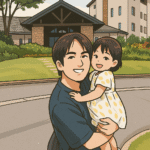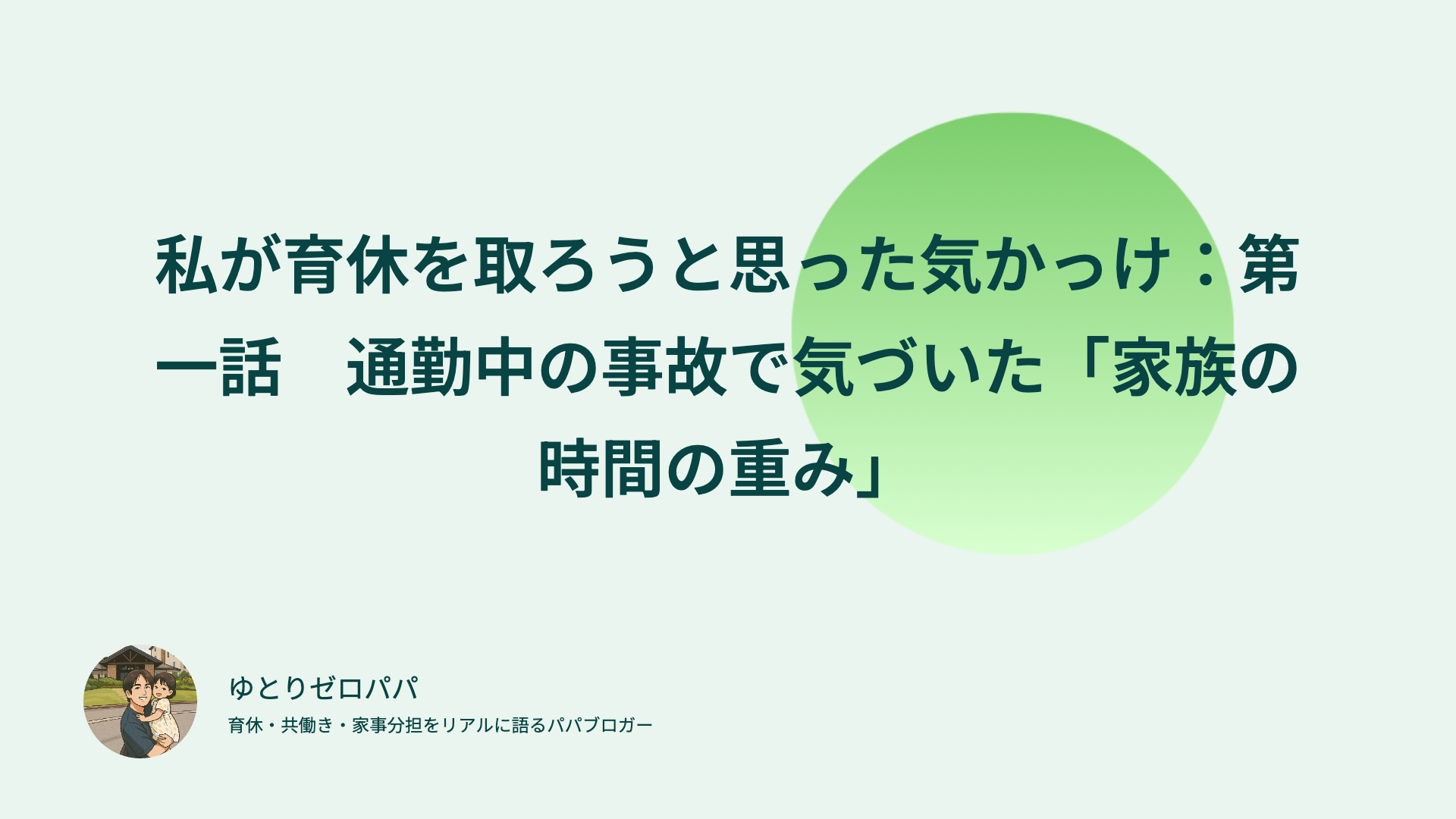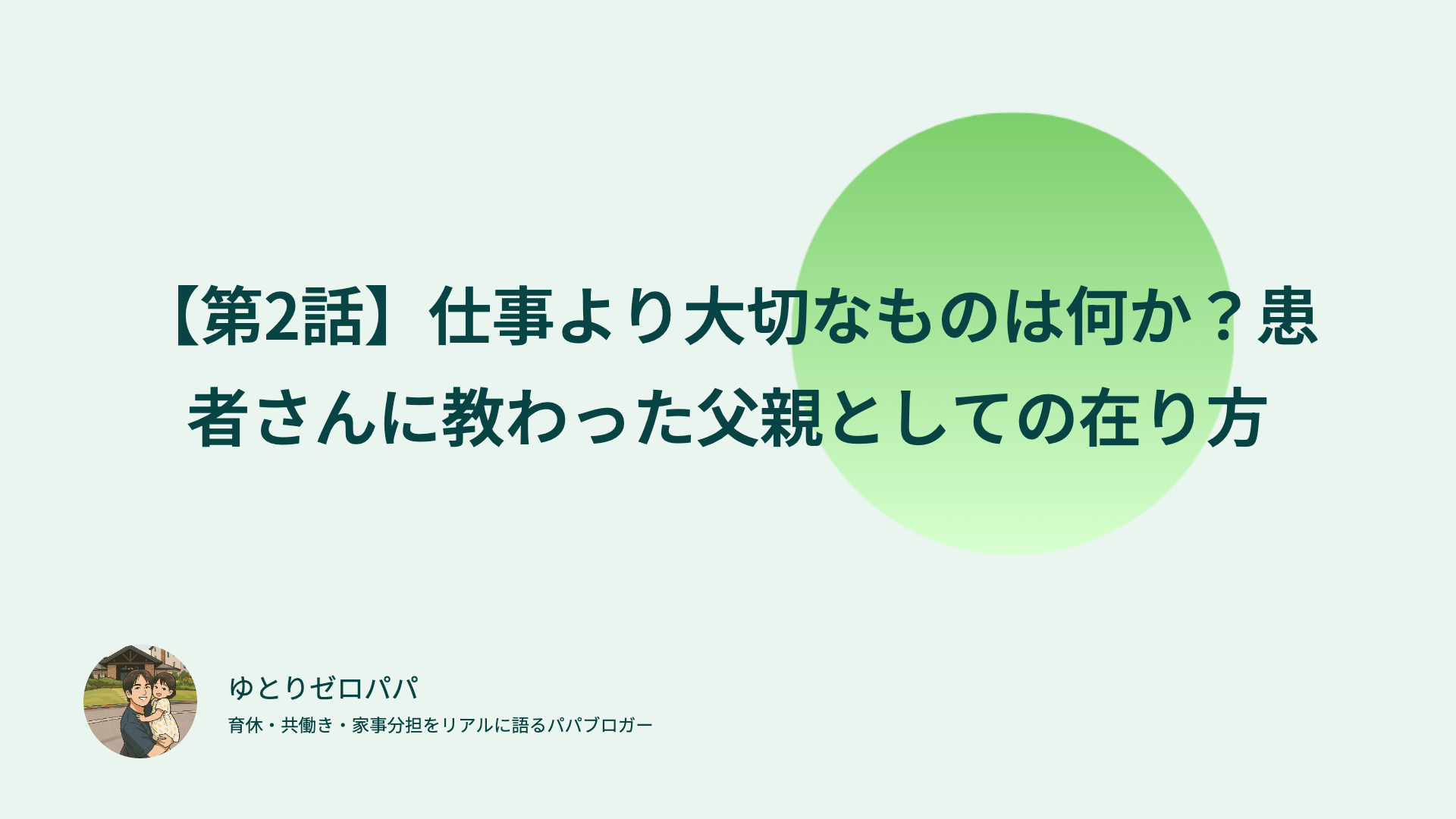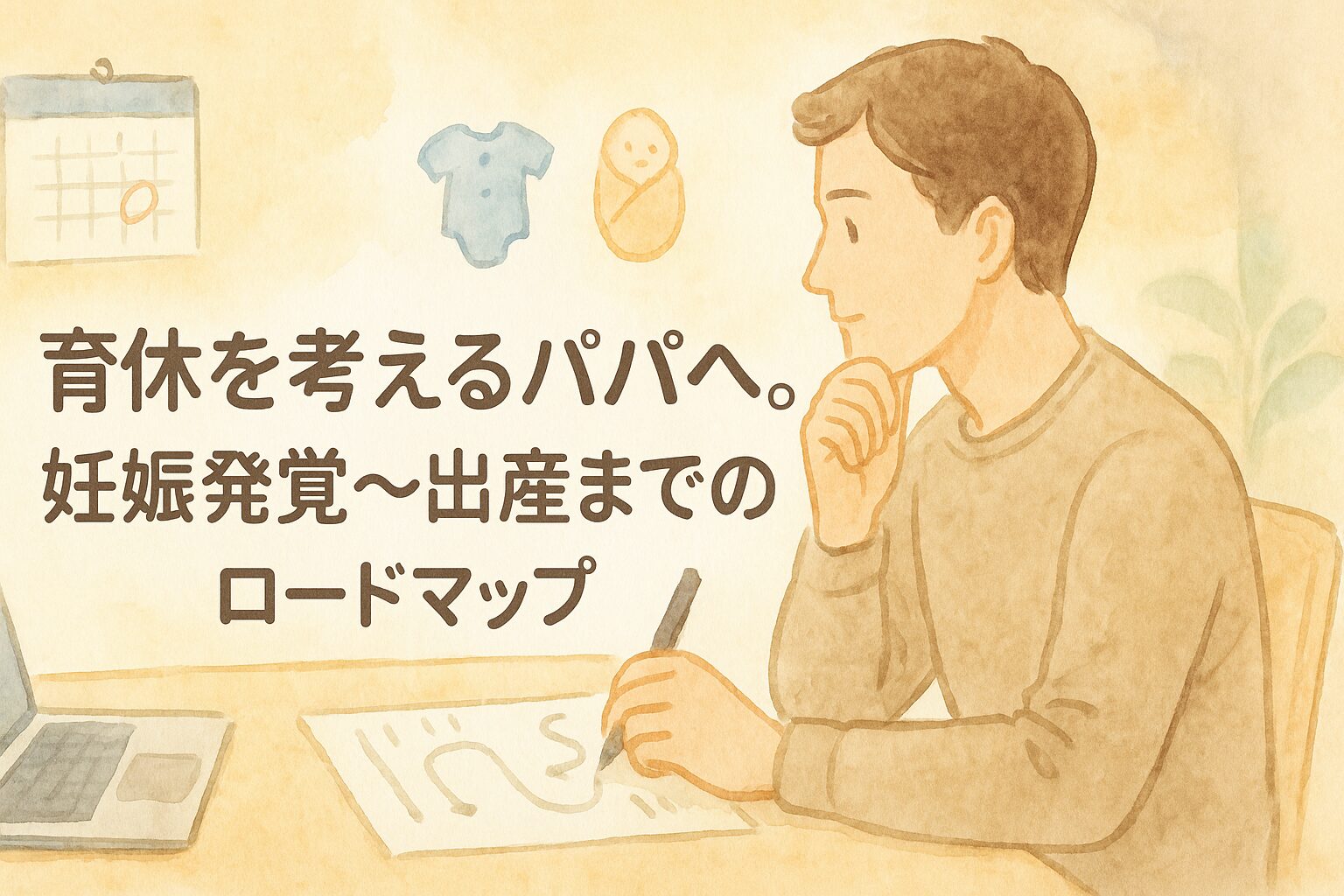産後クライシスを予防した3つの心得|夫婦関係を守るためにパパができること
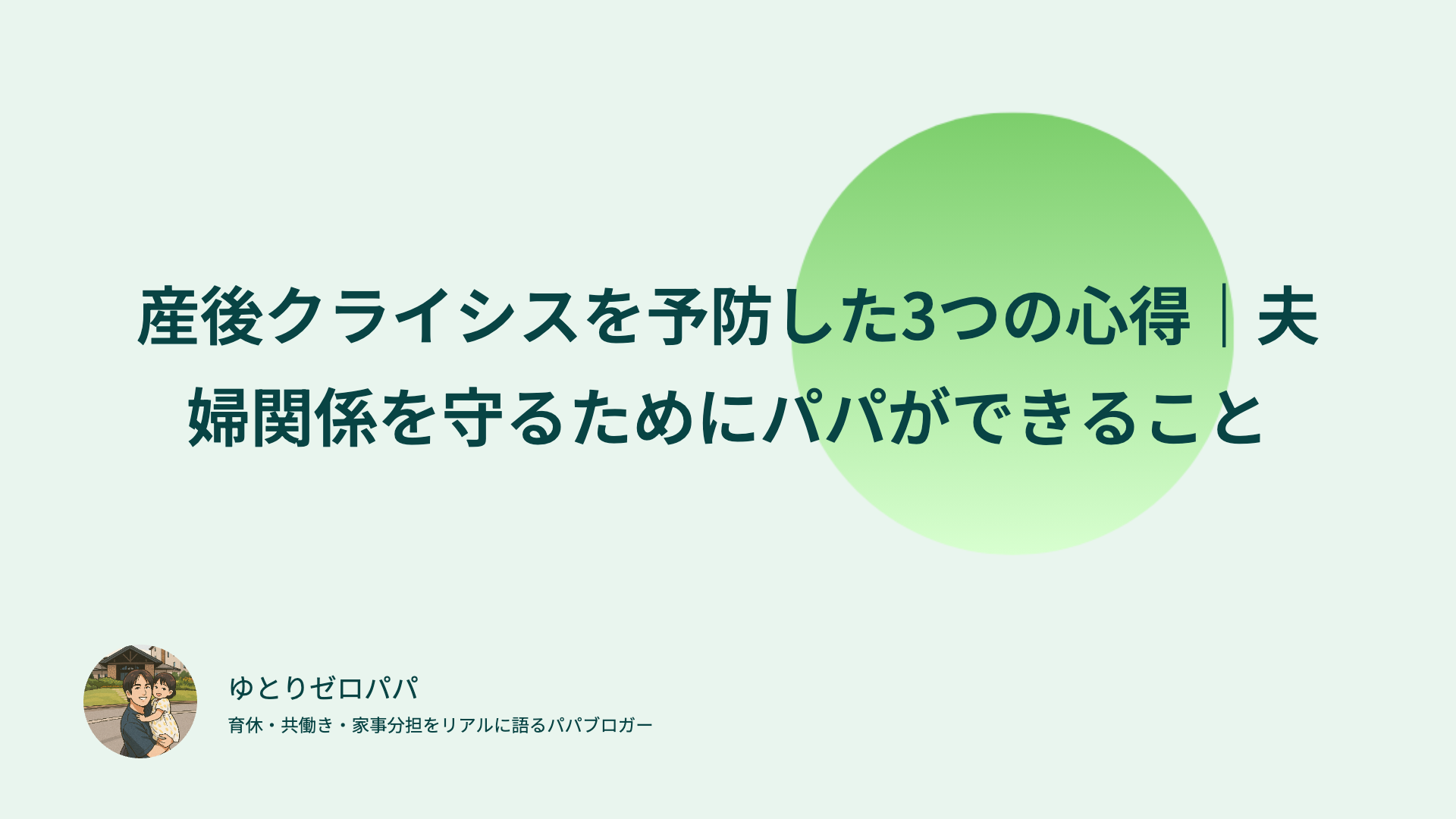
産後クライシスとは?夫婦に突然訪れる「心のすれ違い」
「産後クライシス」って聞いたことありますか?
これは、出産をきっかけに夫婦の関係性が急激に悪化してしまう現象のことを言います。
NHKの調査では、出産後2年以内に「夫婦仲が悪化した」と感じる人は半数以上とも言われています。
私の周りでも、子どもが生まれてさらに仲良くなった夫婦がいる一方で、
「夫の居場所がなくなった」「家庭内がピリつく」といった声も多く聞かれます。
しかも厄介なのは、「そんなのわかってたのに、気づいたらダメだった…」というケース。
だからこそ、事前の準備と意識が何より大事!
この記事では、実際に私が育休を通して意識した
「産後クライシスを防ぐ3つの心得」を紹介します。
① 育休は“積極的に取る”が超重要!受け身はNG
「なんだ、育休取るだけか」と思いました?
でも、ここが一番の分かれ道なんです。
産後クライシスは、実は産前から始まっています。
出産前の妻は「夫は育休を取ってくれるのかな?」「自分が1人で頑張るのかも」と不安を抱えています。
もし「妻に言われて育休を取った」場合、夫は心のどこかで受け身の姿勢になります。
この時点で「主役=妻、補助=夫」という構図ができてしまうんです。
だからこそ、産前のうちに
「育休を取ろうと思ってるんだけど、どのくらい取るのがいいと思う?」
と自分から相談する姿勢を見せることが何より大切です。
「私のことを考えてくれてる」と感じてもらえるだけで、妻の安心感は段違いです。
我が家ではこの段階から“チーム感”が生まれました。
② 完璧を目指さない。5割できたら上出来!
子どもが生まれると、想定外が日常になります。
泣くタイミング、寝ない夜、家事の滞り…。
今までの生活スタイルをそのまま続けるのは無理です。
部屋が散らかるのも、食事がテキトーになるのも、仕方ない。
だから我が家では、産前に話し合って
「5割できたら十分!完璧は目指さない」
というルールを決めました。
SNSで見るキラキラ生活は幻想です。
むしろ、“何とか回してる自分たち”を褒めてあげるくらいがちょうどいい。
特に夫は、「ありがとう」「助かってる」の一言を意識するだけで、
妻のストレスをぐっと減らせます。
我が家の失敗例もあります(笑)。
たとえば洗濯は「妻が分別、夫が洗う・干す」と役割を明確にしてからようやく落ち着きました。
細かく“担当を分ける”ことで喧嘩も減ります。
③ 親や周りを頼る。夫が「橋渡し役」になること
現代の親世代は、「手を出しすぎると嫌がられる」と思って控えていることが多いです。
でも、実際にはサポートがないと絶対に回りません。
ここで大事なのが、夫が調整役になること。
妻が言いづらいことは全部、夫が伝える。
「母さん、助かるけど〇〇の時間だけお願いできる?」と伝えるのも夫の役目です。
そして何よりも、
「俺は妻の味方だから」
という姿勢をハッキリ示すこと。
産後の人間関係トラブルは、本当に深刻なダメージになります。
我が家では、親が近くに住んでいたので、子どもを預けて夫婦でランチやカフェに行く時間を作りました。
小さなリフレッシュが、夫婦関係のガス抜きになります。
まとめ|産後クライシスは「意識」と「行動」で防げる
産後クライシスを予防する3つの心得
1️⃣ 育休は受け身ではなく「積極的に取る」
2️⃣ 完璧を求めず「5割できたらOK」と話し合う
3️⃣ 親や他者を頼り、夫が橋渡し役になる
どれも特別なことではありませんが、
“意識する”だけで結果は大きく変わります。
産後の生活は本当に大変。
でも、チームとして協力できれば、むしろ夫婦の絆は強くなる。
みなさんは、どんな工夫をしましたか?
コメント欄で教えてください。